 かぶ
かぶ読売333って最近よく聞くけど、実際どんな企業が入っているのか分からない…



ETFに連動しているらしいけど、日経平均やTOPIXとどう違うのか気になる…
そう感じている投資家の方は、今とても多いのではないでしょうか。
読売333の構成銘柄は、日本経済を象徴する333社を等しく組み入れた、新しい株価指数です。
業種の偏りを抑えた設計により、長期投資にも安心して活用できる点が大きな魅力です。
指数の中身を正しく知れば、自信を持ってETFなどの投資判断ができるようになります。
分散性・公平性・代表性を備えたこの新指数の中身を、ぜひ一緒に確認していきましょう。
この記事では、資産運用の提案力を高めたい地方銀行勤務の方や、ETFを活用した長期投資を考える個人投資家に向けて、
- 読売333の構成銘柄概要(業種別に整理)
- 日経平均やTOPIXとの比較ポイント
- ETF「MAXIS読売333」の特徴と活用法
上記について、投資歴10年の筆者の視点を交えながら解説しています。
分かりやすく、実務にも活かせる情報を丁寧にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
読売333とは?新しい株価指数の基本を解説


読売333は、2025年3月24日に新たに登場した株価指数で、日本の株式市場における333銘柄を等しく組み入れた「等ウェート型」の構成が特徴です。
日経平均やTOPIXといった既存の主要指数と異なり、特定の大型株に偏らず、広範な業種・企業規模にまたがる分散性の高い設計が魅力とされています。
このセクションでは、読売333の登場背景や設計思想、他指数との違いについて、特に投資判断を担う方々が知っておくべき視点から解説します。
読売333の登場背景と目的



読売333は、読売新聞社が開発した株価指数です。
2025年3月24日から算出が始まり、同日に連動型ETFである「MAXIS読売333日本株上場投信(348A)」も上場されました。
この指数が作られた背景には、次のような目的があります。
- バランス重視の新指標:
時価総額や株価によって銘柄の影響度が偏る従来の指数に対し、等ウェート型を採用することで、より公平で分散性のあるパフォーマンスを目指す。 - 日本経済の“今”を反映:
業種の多様性や新興成長企業も組み入れることで、現在の産業構造に即した代表性を持たせている。 - 投資家への新たな選択肢:
ETF投資や企業分析において、日経平均・TOPIX以外の第三の選択肢としての役割が期待されている。



よくある銘柄偏重型指数では、バランスに不安がある…
と感じていた投資家にとって、読売333はまさにその代替案として注目されています。
日経平均・TOPIXとの違いはここにある
読売333の最大の特徴は、株価加重型や時価総額加重型ではなく、「等ウェート型」で設計されている点にあります。



すべての構成銘柄が指数に対して同じ比率で影響を与えるという仕組みです。
一方、日経平均株価は株価が高い銘柄ほど指数への影響力が強くなる「株価加重型」であり、TOPIXは時価総額の大きな企業が指数に与える影響も大きい「時価総額加重型」です。
そのため、以下のような違いが生じます。
- 読売333(等ウェート型):値がさ株や大型株に偏らず、333銘柄が均等に影響する。中小型株も指数に貢献する設計。
- 日経平均(株価加重型):株価の高い銘柄(例:ファーストリテイリングなど)が大きく影響する。少数の銘柄で変動しやすい。
- TOPIX(時価総額加重型):大型株中心で構成される。経済の規模感は捉えやすいが、成長性より安定性重視。
このように、読売333は「特定銘柄に左右されにくい」という設計思想に基づいており、インデックス投資においてもリスク分散効果を期待できます。
等ウェート設計がもたらすメリットとは
等ウェート型指数である読売333には、いくつかの投資家にとって魅力的なメリットがあります。
特に、資産運用アドバイザーやFPにとっては、顧客への説明やポートフォリオ設計に活用しやすい特性があると言えるでしょう。
- 分散性の高さ:
333社すべてが同じ比重で指数に組み入れられており、特定銘柄や業種の影響が過剰になるリスクを抑えられる。 - 中小型株の存在感:
等ウェート設計により、一般的には埋もれがちな中堅企業にも十分な影響力が与えられるため、新たな成長企業の動向も指数に反映されやすい。 - 値動きの安定性:
値がさ株に依存せず、市場全体の広がりやすさを反映しやすいため、ボラティリティが抑えられる傾向がある。



特定の大型株が急落したら、指数全体も一緒に下がってしまうのでは…
と不安を感じていた方には、等ウェート型の仕組みが心理的な安心材料になるかもしれません。
ただし、リバランス(構成比率の調整)によるコスト増などの課題もあるため、活用する際はETFの仕組みを理解しておくことが重要です。
以上のように、読売333は「公平性」「代表性」「分散性」を備えた新しい指標であり、特にETFを通じて長期投資を目指す方にとって、選択肢の一つとして検討する価値があります。
読売333の構成銘柄一覧を詳しく紹介
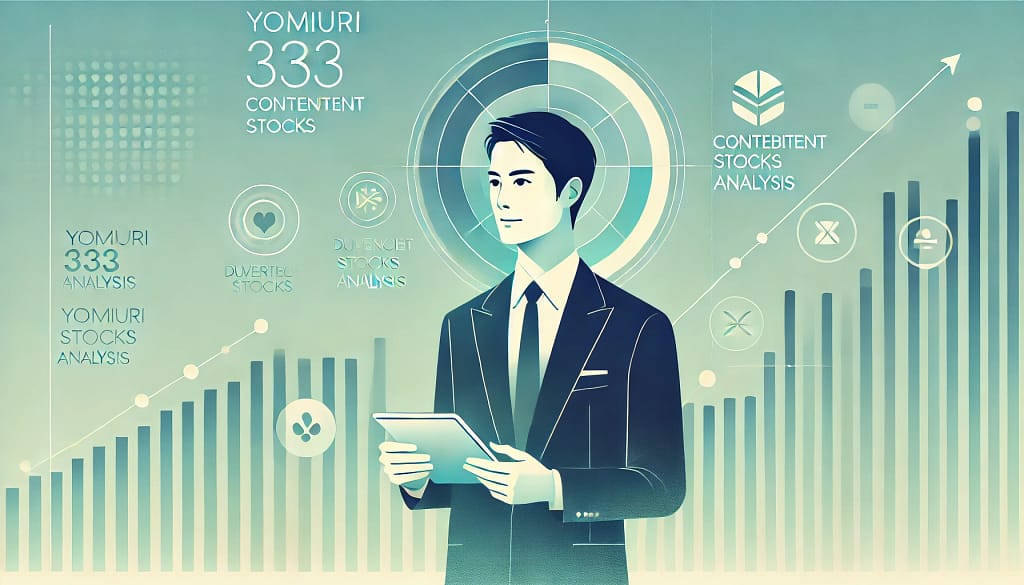
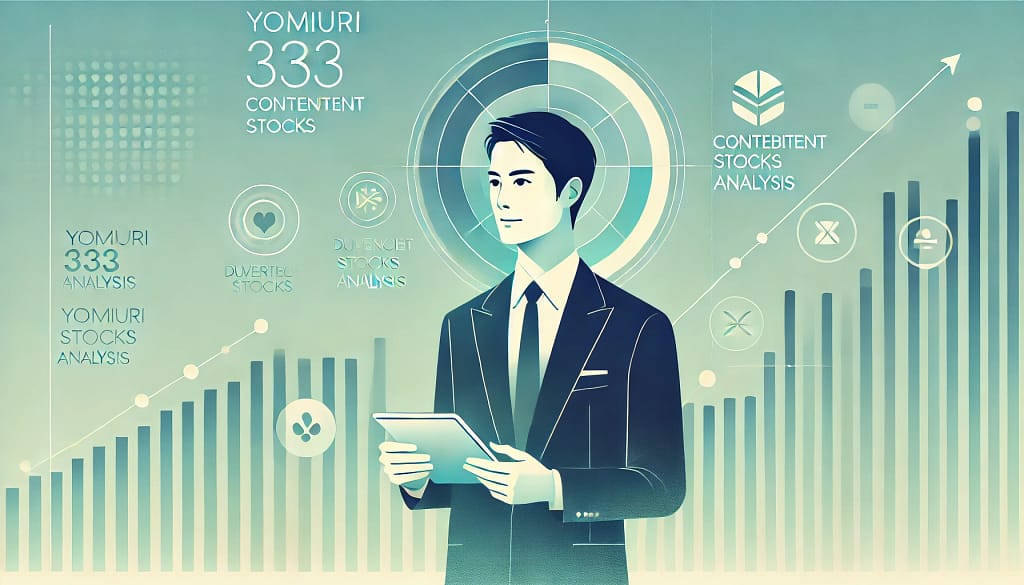
読売333の構成銘柄は、金融、製造、情報通信、医薬品など幅広い業種から選ばれた日本を代表する333社で構成されています。
全銘柄が等しいウエート(均等配分)で組み込まれており、特定企業や業種に偏らない設計が大きな特徴です。
この構成によって、バランスの取れた分散投資が可能となり、指数全体の安定性にもつながります。「どのような企業が採用されているのか」「業種のバランスはどうなっているのか」を把握することで、読売333の性質や投資効果を正しく理解できます。
ここでは、読売333に採用されている構成銘柄の一覧を業種別に整理したうえで、選定基準や構成企業に共通する特徴について詳しく解説します。
採用されている企業名リスト(業種別に整理)
読売333の構成銘柄は、日本取引所グループが公表している33業種分類に基づいて、以下のように分類されています。
各業種からバランスよく企業が選定されており、特定のセクターに偏らない分散がなされています。
主な業種と構成企業の一例は以下のとおりです。
- 電気機器:
ソニーグループ、パナソニック ホールディングス、キーエンスなど。日本の製造業を支える主要企業が多く含まれています。 - 情報・通信業:
NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天グループなど。通信インフラやデジタルサービスを担う企業群です。 - 銀行業・保険業:
三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、第一生命ホールディングスなど。金融セクターの代表格が選定されています。 - 医薬品:
武田薬品工業、エーザイ、中外製薬など。ヘルスケア分野の中核を担う企業が含まれています。 - 卸売業・小売業:
伊藤忠商事、三井物産、セブン&アイ・ホールディングス、イオンなど。国内外の流通を支える大手商社や小売企業が構成されています。
このように、読売333では業種の多様性が重視されており、各業界のトップ企業が網羅的に採用されています。
構成銘柄の一覧は、読売新聞社と三菱UFJ信託銀行が共同で運営する特設ページやETF「348A」の目論見書から確認可能です。
銘柄選定のルールと採用基準
読売333の構成銘柄は、「日本経済の現状と未来を映す333社」として、明確なルールに基づいて選定されています。
主な選定基準は以下のとおりです。
- 上場区分の制限:
プライム市場上場企業を中心に選出。流動性や企業規模の面で一定の水準を満たす企業に限定されています。 - 業種の偏りを抑える調整:
33業種分類を用い、特定業種への集中を避けるよう配慮されています。結果として、業種ごとの採用銘柄数にもバランスが取られています。 - 財務健全性・成長性の確認:
安定した利益水準や自己資本比率、収益性(ROE)など複数の指標を総合的に評価し、一定水準を超える企業のみが対象となります。 - 企業の代表性と社会的評価:
業界内での地位、グローバル展開の有無、ガバナンス体制なども選考要素に含まれています。
これらの基準は、読売新聞社が中心となり、金融機関やアナリストの協力を得て構築されたものです。「公平性」と「透明性」を兼ね備えた選定方針によって、長期的な投資対象としての信頼性が確保されています。
構成企業に共通する3つの特徴
- 業界を代表する存在である
- 長期的な安定性と持続的成長が期待できる
- 企業価値の適正評価に貢献する
各業種で売上・シェア・技術力において突出した実績を持つ企業が中心です。「この業種といえばこの会社」と言えるような顔ぶれが揃っています。
過去の業績に加えて、将来の成長性も重視されています。
例えば再生可能エネルギーや半導体関連企業など、社会的テーマに沿った選定も見られます。
等ウエート方式により、大企業・中堅企業がフラットに評価されることで、市場の過度な偏重を是正し、健全な株価形成を促す役割も担っています。
こうした特徴から、「分散」「公平」「代表性」の3点を重視した指数構成となっており、日経平均やTOPIXとは異なる投資対象として注目されています。
セクター別構成の傾向を読み解く





読売333の最大の魅力は、業種間のバランスが極めて良好であることです。
等ウェートで構成されたこの指数では、特定の業種や企業に偏らず、日本経済の多様な分野をまんべんなく反映しています。
金融・製造・情報通信など、主要産業が均等に配置されているため、市場の一極集中リスクを抑えた設計がされています。
以下では、読売333における「金融・製造・情報通信など主要業種の割合」「業種別の分散性とバランスの強み」「日本経済全体をどうカバーしているか」について詳しく見ていきます。
金融・製造・情報通信など主要業種の割合
読売333の構成銘柄は、金融・製造・情報通信といった日本の基幹産業を中心に、多岐にわたる業種で構成されています。
これは指数の分散性と代表性を高めるための意図的な設計であり、特定セクターへの過度な偏りを防ぐ役割を担っています。
2024年末時点での構成比率(例:MAXIS読売333日本株上場投信の目論見書ベース)を概算すると、以下のような傾向が見られます。
- 製造業(自動車、電機、機械など):全体の約25〜30%
- 金融業(銀行、保険、証券など):約15〜20%
- 情報通信・IT関連:約10〜15%
- 医薬・ヘルスケア:約8〜12%
- 流通・サービス・消費財:約10〜15%
- その他(建設、不動産、輸送など):残りの割合を構成



製造業が多めに感じるかもしれない…
と思う方もいるかもしれませんが、これは日本の経済構造を素直に反映している結果でもあります。
主要業種を押さえながらも、1業種の比率が突出しない点が、読売333の大きな特長です。
業種別の分散性とバランスの強み
読売333のもう一つの強みは、「業種間のバランスが整っていること」です。
この指数は等ウェート型(すべての銘柄を同じ比率で構成)であるため、どの業種が含まれていても、一部の大型株やセクターに影響が偏ることがありません。
これは、時価総額加重型のTOPIXや、株価加重型の日経平均とは明確に異なる点です。
日経平均ではファーストリテイリングやソフトバンクグループなどの値がさ株が大きな影響を及ぼしますが、読売333ではそうした偏りは抑えられています。
全銘柄が等しい比率であるため、以下のような利点が生まれます。
- セクターショックの影響を緩和できる:
特定の業種に悪材料が出ても、指数全体への影響が限定される構造です。 - 業種間の公平な評価が可能になる:
景気循環やトレンドの変化に強く、業種ローテーション戦略にも適応しやすい特徴があります。 - 初心者でも分散効果を実感しやすい:
等ウェート構成は視覚的にも理解しやすく、投資リスクの管理がしやすくなります。
バランスの取れたセクター配分により、安定した資産形成を目指す投資家にも適した設計となっています。
日本経済全体をどうカバーしているか
読売333は「日本経済の縮図」として設計されており、その構成銘柄は国内の幅広い産業を代表しています。
具体的には、以下のような視点で日本経済全体をカバーする工夫がなされています。
- 地域・業種の偏りを排除:
東証プライムを中心に、全国の多様な企業が選定されており、首都圏だけでなく地方企業も数多く含まれています。 - 大企業から中堅企業まで網羅:
時価総額が比較的大きい企業を軸としながらも、知名度だけに依存せず実力ある企業が選ばれている点も特徴です。 - 成長産業と成熟産業のバランス:
製造や金融といった伝統的産業だけでなく、医薬や情報通信、環境・エネルギー関連企業なども含まれ、未来志向の指数となっています。
このように、読売333は単なる上場企業の羅列ではなく、「日本の今とこれから」を映し出す構成となっているのです。
業種の多様性とバランスによって、経済全体の動向を俯瞰できるインデックスとしての価値が際立ちます。
読売333と他の株価指数との比較分析
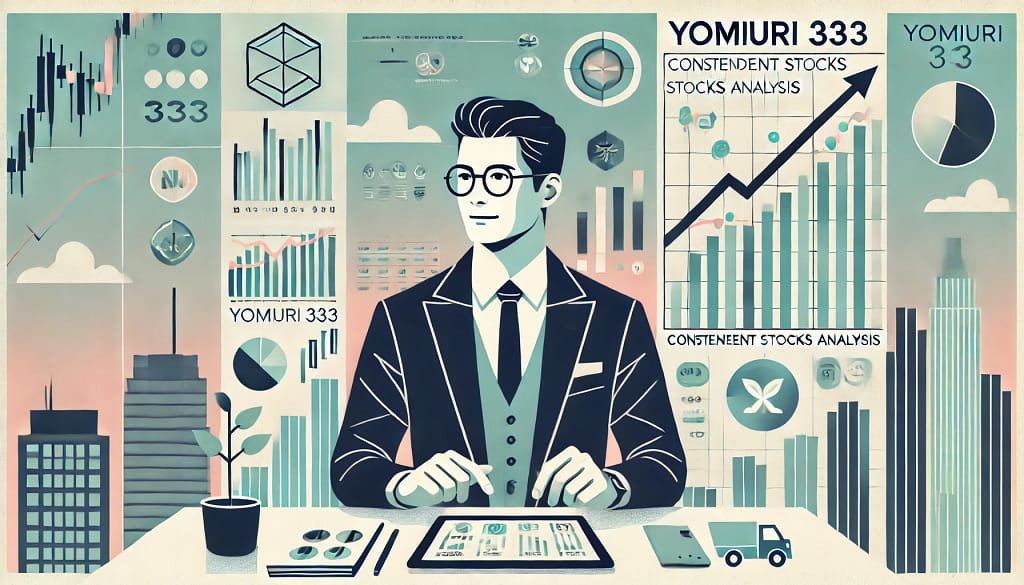
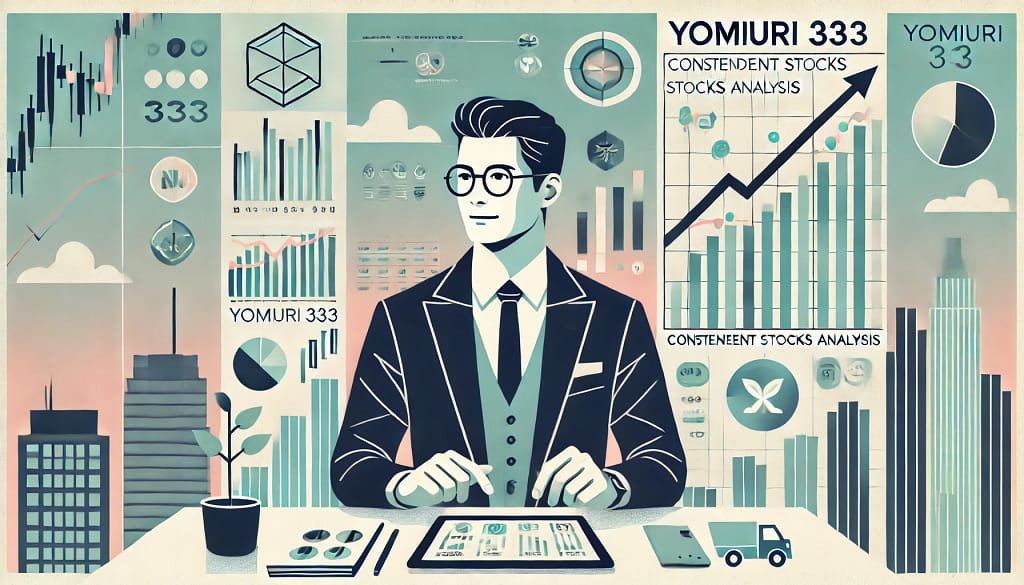
読売333は、日経平均株価やTOPIXとは異なる設計思想に基づいた新しい株価指数です。
特定企業に偏らない「等ウェート型」を採用し、日本経済を構成する多様な業種の333社を均等に組み入れることで、分散性とバランスの良さが際立っています。
これにより、個別の大型株や特定セクターの影響を受けにくいという特徴があります。
ここでは、読売333とTOPIX・日経平均との構成銘柄の重複や違い、指数設計における「値がさ株」への配慮、長期投資におけるメリットについて詳しく見ていきましょう。
TOPIX・日経平均との構成重複と違い
読売333は、既存の代表的な株価指数と重複する銘柄も多い一方で、構成ルールやウエート配分に大きな違いがあります。
まず、TOPIX(東証株価指数)は「時価総額加重型」の代表で、東証プライム市場のほぼ全銘柄をカバーしています。
これに対し、読売333は、厳選された333社のみを対象とした「等ウエート型」であり、対象銘柄数の絞り込みと同等重み付けという点で設計思想が異なります。
日経平均株価は「株価加重型」の指数で、構成銘柄は225社に限られ、1株の価格が高い企業ほど指数に大きな影響を与えます。
つまり、ソフトバンクグループやファーストリテイリングのような“値がさ株”の変動が指数全体を左右しやすい構造です。
読売333では、こうした値がさ株であっても他銘柄と同じ重み付けがされているため、1社の急変によって指数全体が大きく動くリスクを抑えられます。



特定銘柄に左右されにくい指標を選びたい
という方には、読売333の設計は安心材料と言えるでしょう。
値がさ株の影響を抑える仕組みとは
読売333は、各構成銘柄に「均等ウエート(等ウエート)」を割り当てる設計で、これが値がさ株の影響を抑える最大の要因です。
日経平均のように株価の高い企業が指数に与える影響が大きい場合、ファーストリテイリング1社の株価が10%動いただけで、指数全体に大きな変動が生じます。
これは、特定の株価変動が指数全体の方向性を左右してしまうリスクを意味します。
一方、読売333では全銘柄が等しく0.3%程度のウエート(1/333)で構成されており、仮に1社が急騰・急落したとしても、指数全体への影響は最小限に抑えられます。



一部の大型株の上下で振り回されるのが不安…
という方にとって、等ウエート型の設計は精神的にも安心材料となるかもしれません。
ただし、等ウエート型には「頻繁なリバランス(調整)が必要になる」という特性もあります。98羽h6b5
価格変動によりウエートに差が生じた際には、定期的にバランスを取り直す必要があるため、連動ETFの運用コストにも注意が必要です。
長期投資向けの指数としての評価
読売333は、バランスの取れた構成と等ウエート設計により、長期投資に適した指数と評価されつつあります。
その理由は以下のとおりです。
- 分散性の高さ:
333社を業種バランスに配慮して採用しており、特定のセクターへの偏りが小さいため、経済全体の成長に連動しやすいです。 - 公平な構成比率:
各銘柄のウエートが均等で、企業規模にかかわらず同じ影響力を持つ設計です。これにより中堅企業や地方の有望企業も取り上げられやすくなっています。 - テーマ性と代表性の両立:
「日本経済を構成する代表的企業」を主眼に選定されており、投資家が経済全体を俯瞰するためのツールとしても機能します。
特に、日経平均のように“過去の大型企業中心”ではなく、今後の経済を牽引する新興勢力も含んでいる点は、成長性を重視する長期投資家にとって魅力的です。
また、ETF「MAXIS読売333日本株上場投信(348A)」を通じて、指数全体へ手軽に投資できる点も利便性の高いポイントです。
長期的に安定成長を期待したい投資家にとって、読売333は新たな選択肢のひとつとして注目する価値があるでしょう。
読売333に連動するETFとは?投資家の選択肢を整理


読売333に連動するETF「MAXIS読売333日本株上場投信(348A)」は、日本経済を広くカバーする新しい分散型ETFとして注目を集めています。



2025年3月に誕生した読売333は、業種の偏りを抑えた等ウェート型の株価指数です。
この指数に連動するETFを活用することで、初心者でも手軽に日本全体に分散投資できる環境が整いました。
日経平均やTOPIXとは異なり、特定銘柄への過度な依存が少ない設計である点も魅力です。
ここでは、読売333に連動するETF「MAXIS読売333日本株上場投信(348A)」の概要、構成銘柄の比率、リバランスの考え方、そして資産形成への活用方法について詳しく解説します。
ETF「MAXIS読売333日本株上場投信(348A)」とは
MAXIS読売333日本株上場投信(348A)は、読売333に連動する初のETFとして、三菱UFJアセットマネジメントが2025年3月に東京証券取引所に上場しました。
このETFは、読売333の動きに可能な限り連動することを目的としており、指数に含まれる全333銘柄に対して「等しい割合(等ウェート)」で投資します。
つまり、トヨタでも地方の優良企業でも、1銘柄あたりの投資比率は原則同じです。
- 分散効果を重視したい
- 特定の値がさ株に左右されない指数に投資したい
と考えている人にとって、このETFは非常に有力な選択肢となります。
- 上場市場:東京証券取引所(プライム市場)
- 証券コード:348A
- 運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
- 信託報酬:純資産総額に対して、年率0.132%(税抜 年率0.12%)以内をかけた額



信託報酬が安く、日本全体にまんべんなく投資できるETFを探していた
という方にとって、この商品は注目すべき存在と言えるでしょう。
ETFの組み入れ比率とリバランスの考え方
MAXIS読売333の最大の特徴は「等ウェート(均等配分)」での投資です。
通常の指数連動型ETFでは、時価総額が大きい企業の比重が高くなりがちですが、本ETFでは構成銘柄333社すべてに対して、同じ重みで投資が行われます。
これにより、大型株だけでなく、中堅・中小の優良企業にも公平に資金が配分される仕組みとなっています。
ただし、株価の変動によって比率は日々変化します。
そのため、定期的に「リバランス(再調整)」が実施されます。
- リバランスの頻度:年1回(毎年11月を予定)
- 目的:構成銘柄の比率を再び等しい水準に戻すため
- 効果:値上がり銘柄を売却し、値下がり銘柄を買い増す「逆張り効果」が期待される



最近は値がさ株の偏りが気になる…
と感じていた方には、このような仕組みが心強いと感じられるかもしれません。



リバランスは年1回、毎年11月に行い、ウェート調整は年4回、(2、5、8、11月)となります。
読売333ETFを活用した資産形成のヒント
MAXIS読売333を活用することで、初心者でも効率的に日本全体へ分散投資を行うことが可能です。
このETFは、日本の主要業種を広くカバーしており、景気の波に対しても比較的安定したパフォーマンスが期待されます。
具体的には、金融、製造、情報通信、小売、医薬、インフラなど幅広い業種にまたがった構成となっています。
資産形成において本ETFを活用する際のポイントは次の通りです。
- 積立NISAとの相性:
信託報酬が低く、長期保有に適した設計。分散投資効果も高いため、NISA口座での積立投資に適しています。 - ETF特有の流動性メリット:
上場されているため、必要なときに市場で売買できる利便性があります。 - 定期買付の効果:
市場の上下に惑わされず、毎月一定額を購入することでドルコスト平均法の恩恵を受けやすくなります。
「どのETFにすれば安定的に資産を増やせるのか迷っている…」という方は、一度ポートフォリオの中にMAXIS読売333を組み入れることを検討してみてもよいかもしれません。
このETFは、日本経済の幅広い成長に連動する設計であるため、長期目線での資産形成において、安心感のある選択肢となるでしょう
【FAQ】読売333に関するよくある疑問を解消


読売333に関する疑問は、指数の特性やETF投資との関係を正しく理解することで解消できます。
特に「日経平均やTOPIXと比べてどちらが有利なのか」「銘柄はどう見直されるのか」「初心者でも投資してよいのか」といった疑問は、投資判断の安心材料として多くの人が気になるポイントです。
ここでは、読売333に関する代表的な3つの疑問に絞り、順を追って明確に解説していきます。
日経平均やTOPIXとどちらが投資向き?
読売333は、日経平均やTOPIXと比較して「分散性」と「公平性」に優れており、中長期投資に適した設計といえます。
まず、日経平均株価は225銘柄で構成される株価加重型の指数で、1株あたりの価格が高い企業の値動きに強く影響されます。
つまり、値がさ株の動きによって指数全体が大きく変動する可能性があります。
一方、TOPIXは時価総額加重型で、時価総額の大きい企業ほど指数に与える影響が大きくなります。
これは、巨大企業への偏重を意味することがあり、「市場全体の代表」としては機能しますが、特定企業のリスクも抱えがちです。
対して読売333は「等ウェート型」を採用しており、333社それぞれが同じ比率で構成されるのが特徴です。
これにより、特定の企業や業種の偏りを抑え、バランスよく日本経済を反映する設計になっています。



一部の銘柄に振り回されたくない
と感じる投資家にとって、読売333は安心感のある選択肢になり得るでしょう。
今後の見直しや銘柄入替のタイミングは?
読売333は、年に1回の定期見直しによって銘柄の入れ替えが行われる予定です。
読売新聞社が発表している資料によると、読売333の構成銘柄は「業種バランス」「市場代表性」「財務健全性」などを考慮して選定されています。
これらの基準に基づき、毎年定期的にスクリーニングを行い、入替えが必要と判断された場合には新たな企業が採用される仕組みです。
また、臨時の見直しとして、上場廃止や経営破綻など特別な事情が生じた場合には、定期見直しを待たずに入替えが実施されることもあります。



いつ変更されるのか気になる…
という方は、読売新聞社や連動ETFの運用会社(三菱UFJアセットマネジメントなど)の公式発表をチェックすることで、タイムリーな情報を得られるでしょう。
初心者でも読売333に連動したETFに投資できる?
読売333に連動したETF(MAXIS読売333日本株上場投信)は、投資初心者でも活用しやすい金融商品です。
最大の理由は、指数自体が等ウェートで設計されているため、個別銘柄の値動きに左右されにくく、リスクが比較的分散されていることにあります。
さらに、ETFとして上場しているため、株式と同じように証券会社で売買できる点も魅力です。
投資信託に比べてコストが低く、リアルタイムで取引ができる点もETFの利点と言えます。
特に「積立NISA」や「長期保有型の分散投資」を志向する方にとっては、安定的に運用できる選択肢のひとつになるでしょう。
「ETFは難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、証券口座を開設し、ETFのコード「348A」を入力するだけで購入できます。
事前に構成銘柄の業種やバランスをチェックすれば、より安心して投資に踏み出せるはずです。
まとめ:読売333で広がる新たな分散投資の可能性


今回は、日本株の新たな指標を探している投資家や資産運用に関心のある方に向けて、
- 読売333の特徴や設計思想(等ウェート型・333社構成)
- 構成銘柄一覧と業種別のバランス分析
- ETF「MAXIS読売333日本株上場投信(348A)」の連動性と活用法
上記について、長期投資家としての実体験や視点を交えながらお話してきました。
読売333は、特定銘柄に偏らない公平性と、幅広い業種をカバーする多様性に優れた新しい株価指数です。
得られた情報を活かせば、過度な集中リスクを避けつつ、着実な資産形成のための判断材料が増えるでしょう。
ETF投資を検討している方は、構成銘柄とセクター比率を確認することで、より納得感のある一歩を踏み出せるはずです。
- 総合力&取引シェアNo.1!
- 楽天ポイントで株が買える&貯まる!
銘柄スカウターでの分析、IPO投資に挑戦したい人に!
- 世界最多水準(米国株)の取引銘柄&最安の手数料!
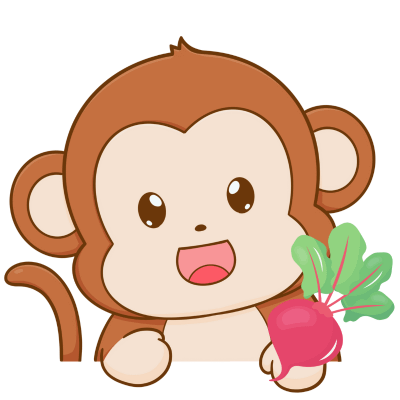


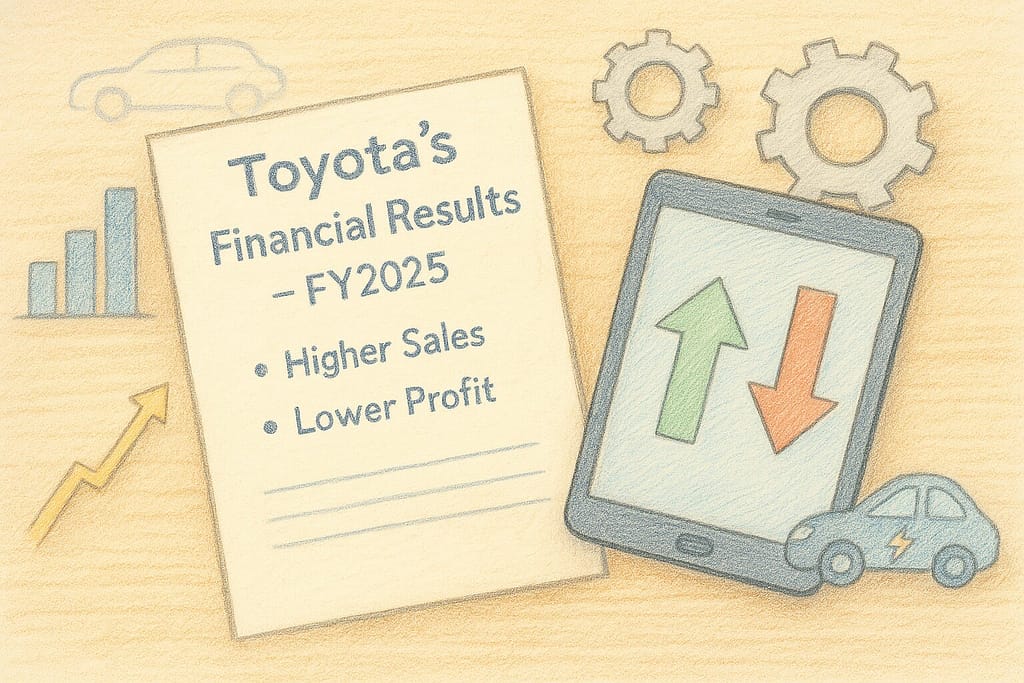

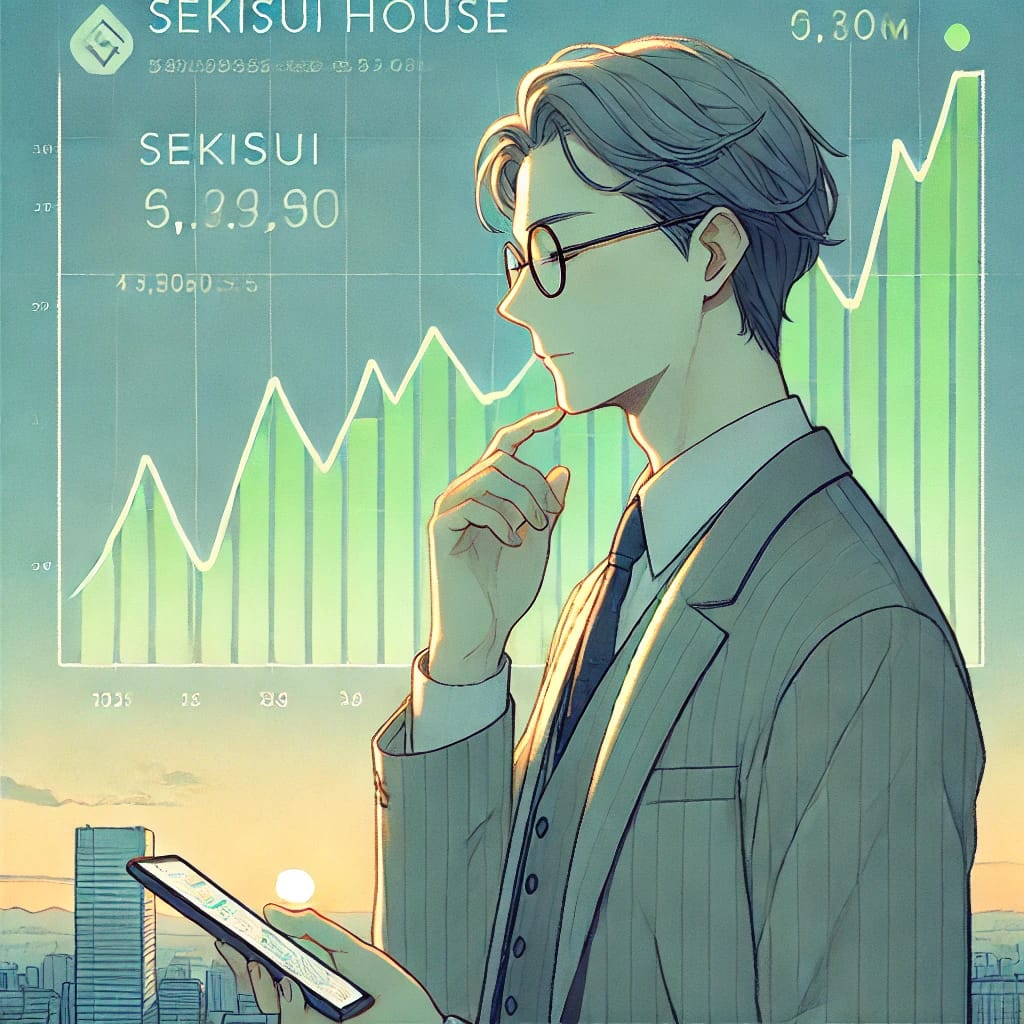
コメント